| 年号 |
月 日 |
|
年齢 |
|
内容 |
| 1924 |
5 |
|
28 |
|
テアトル・ド・ラ・シガールで「雲のハンカチ」上演。
|
| --- |
|
" |
|
「Sept Manifestes Dada(七つのダダ宣言)」出版。 |
|
| 1925 |
--- |
|
29 |
|
スウェーデン生まれの女流画家で、父親がマッチ産業で大成功したグレタ・クヌートソンと結婚。
莫大な財産が手に入る。

グレタとトリスタン |
| --- |
|
" |
|
 「Mouchoir de nuages(雲のハンカチ)」出版。 「Mouchoir de nuages(雲のハンカチ)」出版。
ホアン・グリスによるエッチング |
|
| 1926 |
--- |
|
30 |
|
アドルフ・ロースの設計による邸宅建築。シュルレアリストらの会合にもよく使われることになる。
森鴎外と岡本太郎ものちにここを訪れ、晩年のツァラと日本の地震についての話をする。
 |

家のプレート |
| ツァラの家 |
|
 |
 |
| 家のドア。今は違う人が住んでいる。 |
ツァラの家はこの道の奥(ちょうど木が重なり合う
ところ)にある。モンマルトルのジュノー通り。 |

奥さんと、屋上で。 |

1930年の部屋の様子 |
|
|
| 1927 |
--- |
|
31 |
|
息子クリストフ・ツァラ生まれる。彼は後年物理学者となる。

左からクリストフ、グレタ、トリスタン
|
|
| 1928 |
--- |
|
32 |
|
「Indicateur des chemins de coeur(心の運行時刻表)」出版。 |
|
| 1929 |
12 |
|
33 |
|
 |
「La Revolution Surrealiste(シュルレアリスム革命)」誌12号(最終号)に『L'homme approximatif(近似的人間)』の最終詩章を掲載。ブルトンと公式に和解をし、シュルレアリスム陣営に加わる。
これまでの数年間、いくつかの出版物を刊行したほかほとんど沈黙を守っていたツァラは、フロイトやユングなどの夢や無意識に関する学問に傾倒していた。ブルトンらシュルレアリストたちがフロイト寄りだったのに対して、彼はユングを支持していた。

左からブルトン、エリュアール、ツァラ、ペレ。1932年。
|
|
| 1930 |
--- |
|
34 |
|
「L'arbre des voyegeurs(旅人たちの樹)」出版。 |
|
| 1931 |
12 |
|
35 |
|
「革命に奉仕するシュルレアリスム」誌4号に、後期のツァラの詩論の柱となる「詩の状況に関する詩論」を発表。 |
| --- |
|
" |
|
「L'homme approximatif(近似的人間)」出版。クレーの版画つき。
 
現在出版されているもの。 クレーによるエッチング |
|
| 1932 |
--- |
|
36 |
|
「革命的作家芸術家同盟」(A.E.A.R)に参加。 |
| --- |
|
" |
|
「Où boivent les loups(狼の水のみ場)」出版。 |
|
| 1933 |
--- |
|
37 |
|
「革命に奉仕するシュルレアリスム」誌6号に『種子と表皮』の一部掲載。 |
| --- |
|
" |
|
「L'antitête(反頭脳)」出版。

ピカソによる反頭脳のためのエッチング。 |
|
| 1934 |
--- |
|
38 |
|
ルネ・クルヴェルと共にアラゴンの設立した「文化の家」に参加。

写真は1922年、ツァラ26歳のときのもの。左からクルヴェル、
ツァラ、ジャック・バロン。マン・レイ写す。
|
| --- |
|
" |
|
ルーマニアで「Primele Poeme ale lui Tristan Tzara urmate de Insurecita de la Zürich(初期詩篇)」出版。 |
|
| 1935 |
3 |
|
" |
|
雑誌「カイエ・デュ・シュッド」誌に公開書簡を発表、シュルレアリスムからの離脱を表明。 |
| 6 |
|
39 |
|
「革命的作家芸術家同盟」による「文化擁護国際作家会議」で、「先駆者と新入者」という講演を行う。これは同同盟機関紙「コミューヌ」に掲載された。
 |
|
 |
| 文化擁護国際作家会議 |
|
ツァラのクローズアップ |
|
| --- |
|
" |
|
「Sur le champ(遅滞なく)」出版。 |
|
| 1936 |
6 |
|
40 |
|
アラゴン、カイヨワ、モヌロとともに「人間現象学研究グループ」設立、雑誌「アンキジシオン」誌刊行。 |
| --- |
|
" |
|
「Ramures(広がる枝)」出版。 |
|
| 1937 |
--- |
|
41 |
|
スペイン文化擁護委員会書記としてマドリード、バレンシアで第二回国際作家会議を組織する。 |
| --- |
|
" |
|
「Vigies(見張り番)」出版。 |
|
| 1938 |
--- |
|
42 |
|
グレタと離婚状態になる。 |
| --- |
|
" |
|
「La deuxième aventure céleste de Monsieur Antipyrine(アンチピリン氏の第二の天上冒険)」出版。 |
|
| 1939 |
--- |
|
43 |
|
「Midis gangés(真昼を勝ち取って)」出版。 |
|
| 1940 |
--- |
|
44 |
|
第二次世界大戦中、右翼の「ジュ・スイ・パルトゥ」紙に非難され、ゲシュタポの追及を受けたツァラは、この年から五年間、アラゴンらとともに「作家全国委員会」のメンバーとして、フランス南西部で対ドイツ地下抵抗運動に参加する。地下出版された諸雑誌に「T.Tristan」の名前で協力し、自らも雑誌「ル・ボワン」誌の編集に携わる。ツールーズで「知識人センター」議長を務め、「レジスタンス文学放送」を主宰。解放後はオック語研究所の設立に尽力する。アメリカへ飛んだブルトンとは違い、彼はフランスに留まっていた。 |
|
| 1944 |
--- |
|
48 |
|
「Une route seul soleil(ひとつの道唯一の太陽)」出版。 |
|
| 1946 |
1 |
|
49 |
|
ヴィエー・コロンビエ座で『逃走』上演。上演中にイジドール・イズーらレトリズムの若者たちが客席からレトリズムの宣言をし、一時舞台は若干混乱する。 |
| --- |
|
50 |
|
スイス、ユーゴスラヴィア、ルーマニア、ハンガリー、チェコ等の各国で講演を行う。

サンジェルマン・デプレでの祝50歳パーティー |
 |
|
ツァラのクローズアップ |
|
| --- |
|
" |
|
「Le coeur à gaz(ガスで動く心臓)」「Entre-temp(時を縫って)」「Le signe de vie(生のしるし)」「Terre sur terre(地上の地)」出版。 |
|
| 1947 |
4/11 |
|
" |
|
ソルボンヌ大学で「シュルレアリスムと戦後」という講演を行う。彼はレジスタンスにおけるシュルレアリスムの不在(事実ブルトンは戦中アメリカに飛んでいた)を非難し、「歴史はシュルレアリスムを乗り越えた」と言い切るが、そこでブルトン達の介入を受け場内は騒然となり、ツァラの声はほとんど聞き取れなかったという。
 |
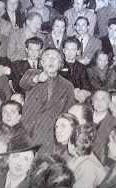 |
| 立ち上がって何かを叫ぶブルトン。ソルボンヌ大学にて。 |
ブルトンのアップ |
会場はシュルレアリストたちの対決の場となる。またしてもツァラとブルトンは訣別し、二人は結局最後まで許しあうことはなかった。
|
| --- |
|
51 |
|
フランスに帰化し、フランス共産党に入党。戦後の彼の活動は、ダダイストというよりも、彼がそれを望んだかは別として「レジスタンスの詩人」として人びとに認識されることになる。 |
| --- |
|
" |
|
「Morceaux(詩選集)」「La fuite(逃走)」「Le surréalism et l'aprés-guerre(シュルレアリスムと戦後)」出版。 |
|
| 1949 |
--- |
|
53 |
|
「Phases(諸相を経て)」「Sans coup férir(戦わずして)」出版。 |
|
| 1950 |
--- |
|
54 |
|
リブモン・デセーニュとラジオ対談を行う。
トルコ詩人、ナジム・ヒクメットの釈放を求める「ナジム・ヒクメット擁護委員会」の議長として尽力。 |
| --- |
|
" |
|
「Parler seul(ひとり語る)」出版。 |
| --- |
|
" |
|
「De mémoire d'homme(記憶にある限り)」出版。 |
|
| 1951 |
--- |
|
55 |
|
チュニジアの大学の招きにより講演を行う。 |
| --- |
|
" |
|
「Le poids du monde(世界の重み)」出版。 |
|
| 1952 |
--- |
|
56 |
|
「La premiére main(最初の手)」出版。 |
|
| 1953 |
--- |
|
57 |
|
「Europe」誌に「身振り、句読法、詩的言語」発表。
ローマでピカソについて講演を行う。
 上がツァラ、下がピカソ。1950年。 上がツァラ、下がピカソ。1950年。 |
| --- |
|
" |
|
「La face intérieure(内面の顔)」出版。 |
|
| 1954 |
--- |
|
58 |
|
「L'Egypte face à face(エジプトと向き合って)」出版。 |
|
| 1955 |
--- |
|
59 |
|
「A baute flamme(炎を高く)」「La bonne heure(折り良し)」「Miennes(わが辿りし)」出版。 |
|
| 1956 |
--- |
|
60 |
|
動乱直前のハンガリーのブタペストを訪問、パリに戻るとハンガリーの自由化闘争を支持(ソ連からの自由化、つまり反共産党の立場になる)し、アラゴンら共産党の知識人の見解との相違を表明する。それは党に対する明確な批判の形はとっていなかったようだが、この事件は晩年のツァラの孤立いっそう深めることになる。このあとツァラは、ヴィヨンやラブレーといった詩人のアナグラムの研究に没頭する。 |
| --- |
|
" |
|
「Le fruit permis(許された果実)」出版。 |
|
| 1957 |
--- |
|
61 |
|
「Frére bois(森は兄弟)」出版。 |
|
| 1958 |
--- |
|
62 |
|
「La rose et le chien(薔薇と犬)」出版。 |
|
| 1960 |
--- |
|
64 |
|
サルトル、ボーヴォワール、ブルトン、ロブ・グリエらとともに、アルジェリア独立闘争を支持する「121人宣言」に加わる。 |
|
| 1961 |
--- |
|
65 |
|
タオルミナ国際詩人大賞を受賞。受賞者にはほかにギリエン、クワジーモド、シュペルヴィエルらがいる。 |
| --- |
|
" |
|
「Juste présent(まさしく今)」出版。 |
|
| 1962 |
--- |
|
66 |
|
ローデシアでの「アフリカ文化会議」に出席。 |
| --- |
|
" |
|
「De la coup aux lèvres(詩選集――盃から唇への旅路)」出版。 |
|
| 1963 |
--- |
|
67 |
|
「Sept Manifestes Dada Lampisteries(七つのダダ宣言 ランプ製造工場)」出版。 |
| --- |
|
" |
|
12月24日、パリのリール街5番地のアパルトマンにて死去。 |
→トップに戻る
|